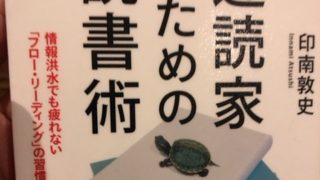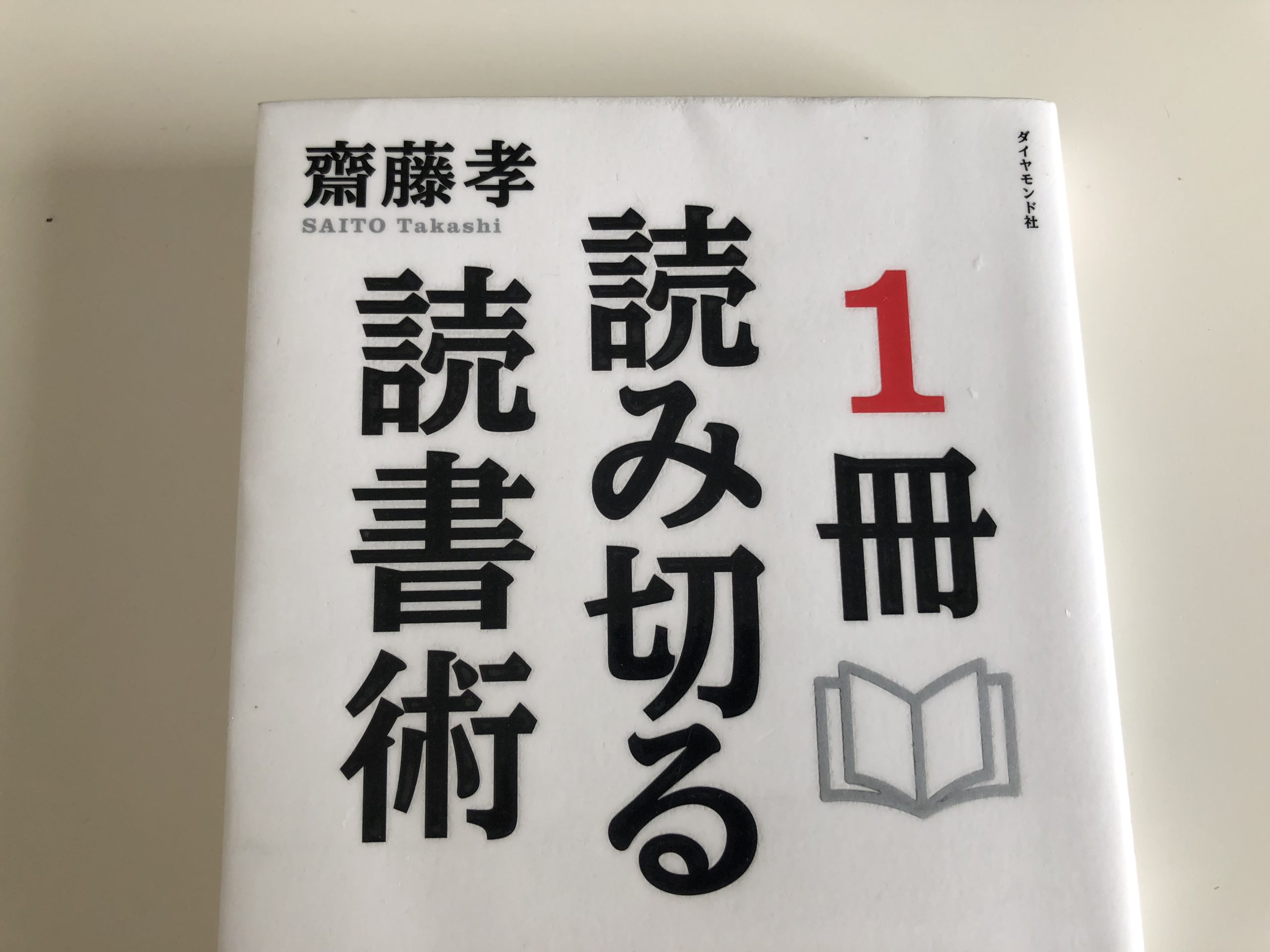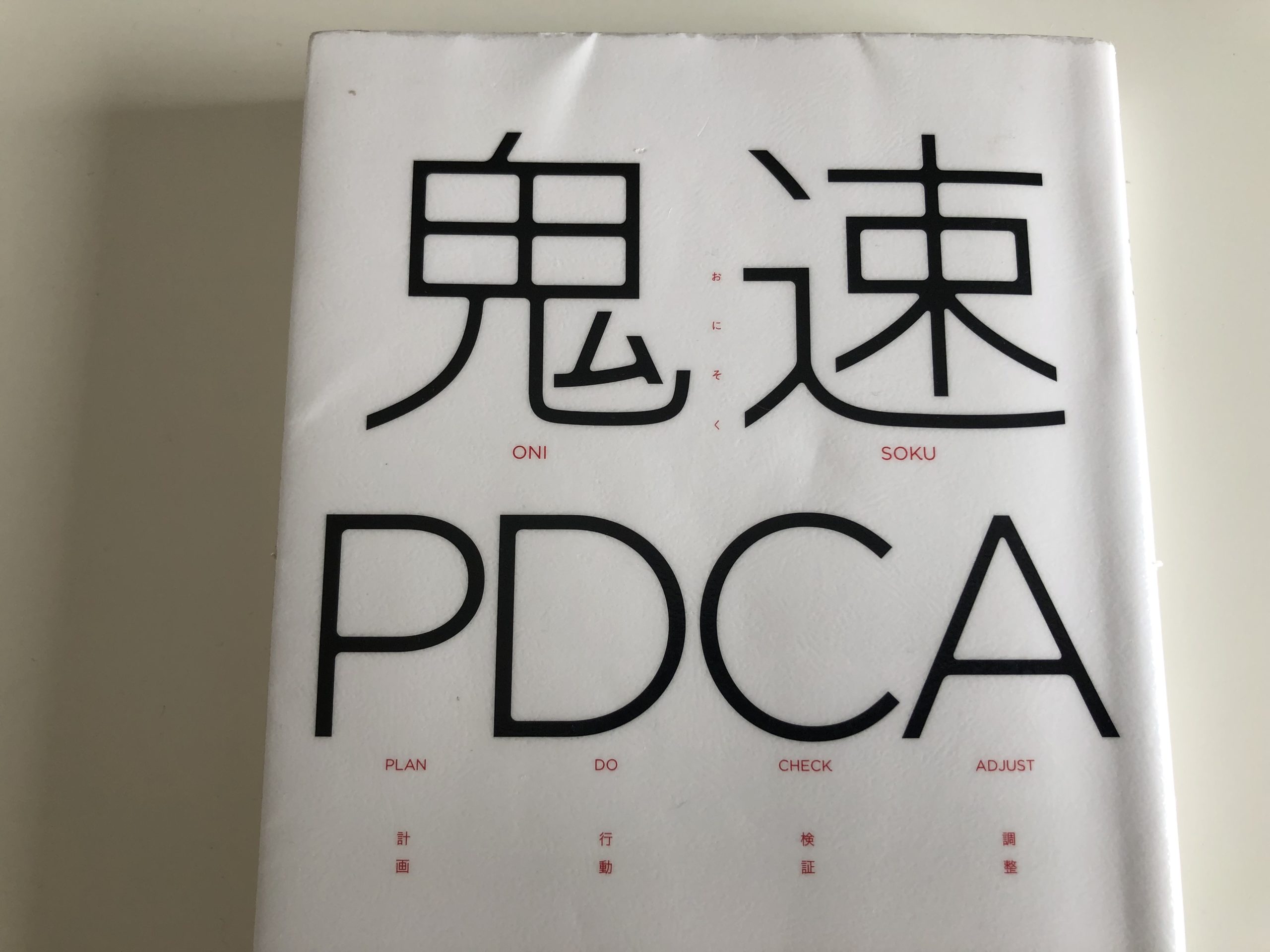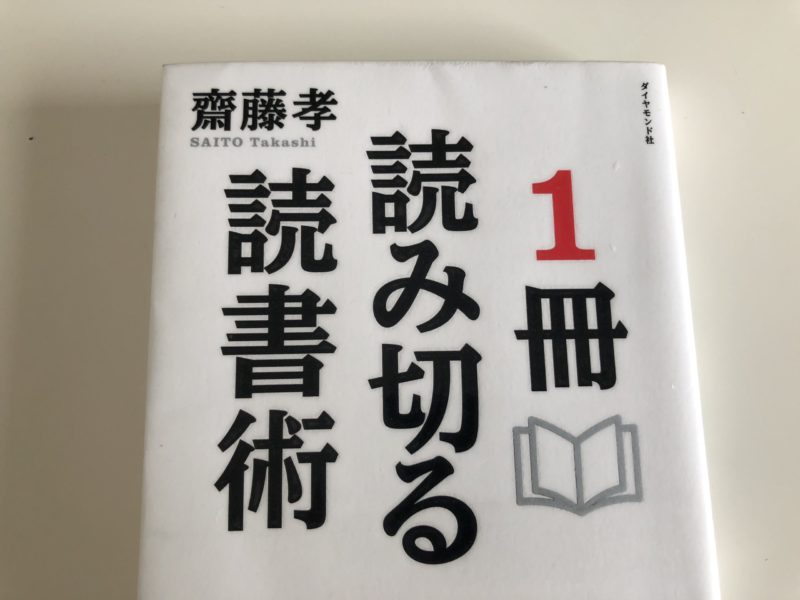
今年に入って「読みたいけれど読めない」という時期が少し続いていたので、読書の勢いをつけるために齋藤孝さんの「1冊読み切る読書術」という本を手にとってみました。
今回の「1冊読み切る読書術」でもまた良い発見がありました。
30分1冊勝負
本はついつい一言一句正確に読まないといけないと思ってしまうのが自分の悪い癖です。真面目に読まないを忘れかけていた
本が読めない理由の一つに「本を読む時間を無制限に設定している」ということがあると著者はいいます。いつでも読めると思うからいつまでも読まない。
なので、1冊を30分で読み切ると決めて読む。
30分で1冊読むためには、「書面にサーチライトを当てるようにページ全体」に目を流して、引っかかったところだけを読むようにします。
アウトプットを意識して読む
自分もまさにそうですが、インプットをしようと思って読んでも、本の内容を1割も覚えてないのが正直なところです。特に熟読した本に限って、読み切ることが目的になってしまい、あとから考えると読んだという事実だけが残っていて、中身はあまり覚えていなかったりします。
逆に時間がなくて、気になるところだけをさーっと流し読みした時のほうがその本の内容を覚えていることがあります。
本書を読んで、その理由がわかりました。
自分がアウトプットを意識して読んでいるからなんですね。
アウトプットを意識して読むとは、「読んだあとに良かったと思うところを3つ言えるようにしておく」、「どこがどう面白かったか」を3つ言えるようにしておくことと著者は言っています。
面白かった内容の3つは、前半で1つ、中盤で1つ、終盤で1つと上げていくと、1冊をバランスよく語ることができます。
アウトプットをする際には、ビフォーアフターを意識
ビフォーアフターの変化を書く時に意識するポイントは3つです。
- 読む前はどういう印象を持っていたか
- 実際に読んでみてどうだったか
- ターニングポイントはどうだったか
ターニングポイントが少し難しく感じますが、実際に読んでみて心境が変わったところがターニングポイントなので、その辺のエピソードを上げるのが良いです。
さらに投稿前には、以下をチェックする
- 熱くなりすぎてわかりにくい表現になっていないか
- 人を傷つけてしまう表現をしていないか
- 日本語の文章として正しいか
日本語の文章として気をつけないといけないのは、主語と述語がきちんと対応した簡潔な文章を書くということです。ついつい長い文章になりがちなので、一文を短く区切ってわかりやすい文章にする。
本書では他にも「本を買ったらカフェに飛び込む」や「週1冊で成功体験をつむ」などすぐにできることから、著者のおすすめの本も多数紹介されています。
最終的には、「罪と罰」や「カラマーゾフの兄弟」などの長文小説を読破するのが目的と言われており、本書の内容を試してみて、最終的に挑戦してみたいと思います。
読書術については、以前読んだ「遅読家のための読書術」も良かったです。