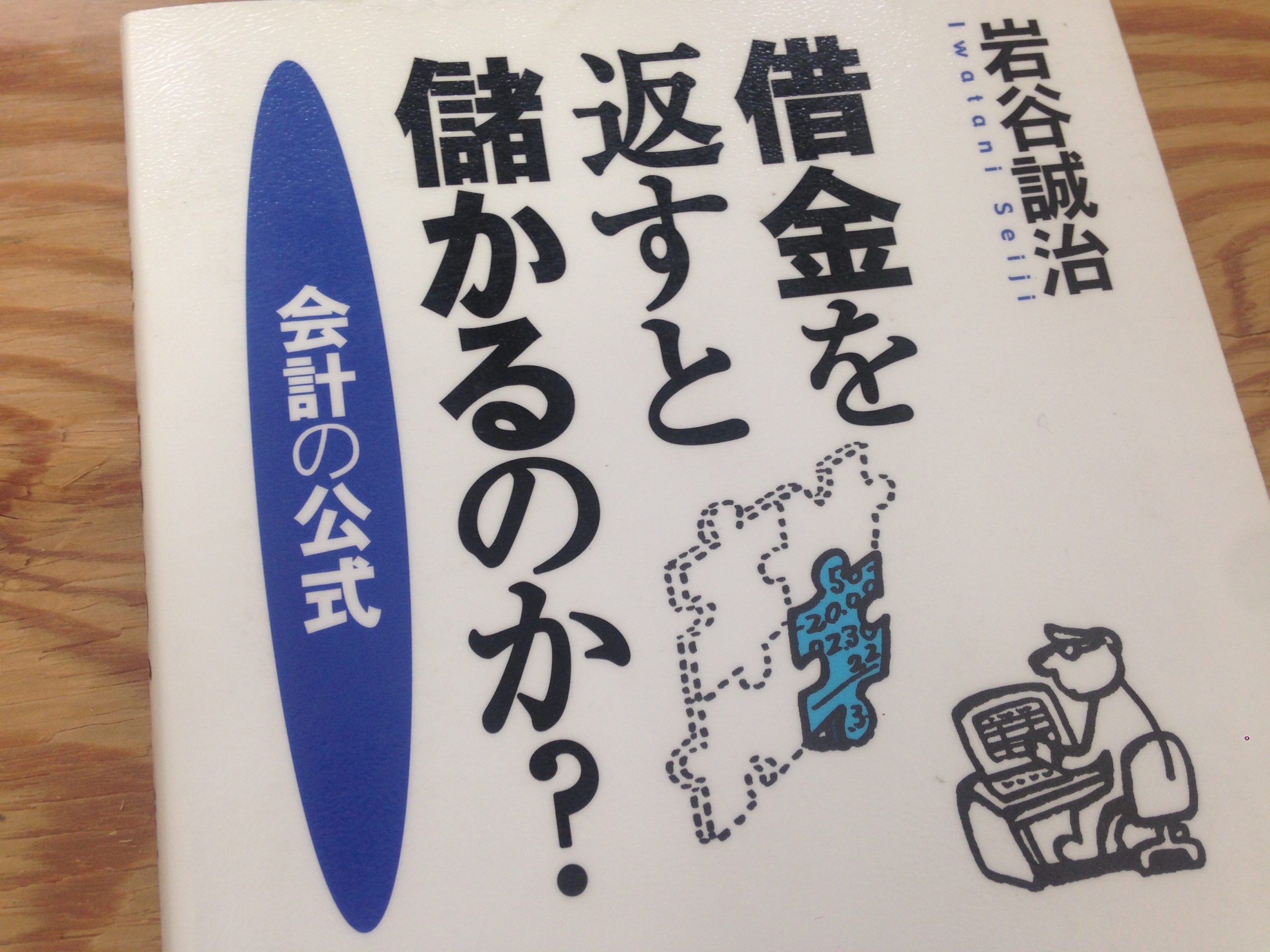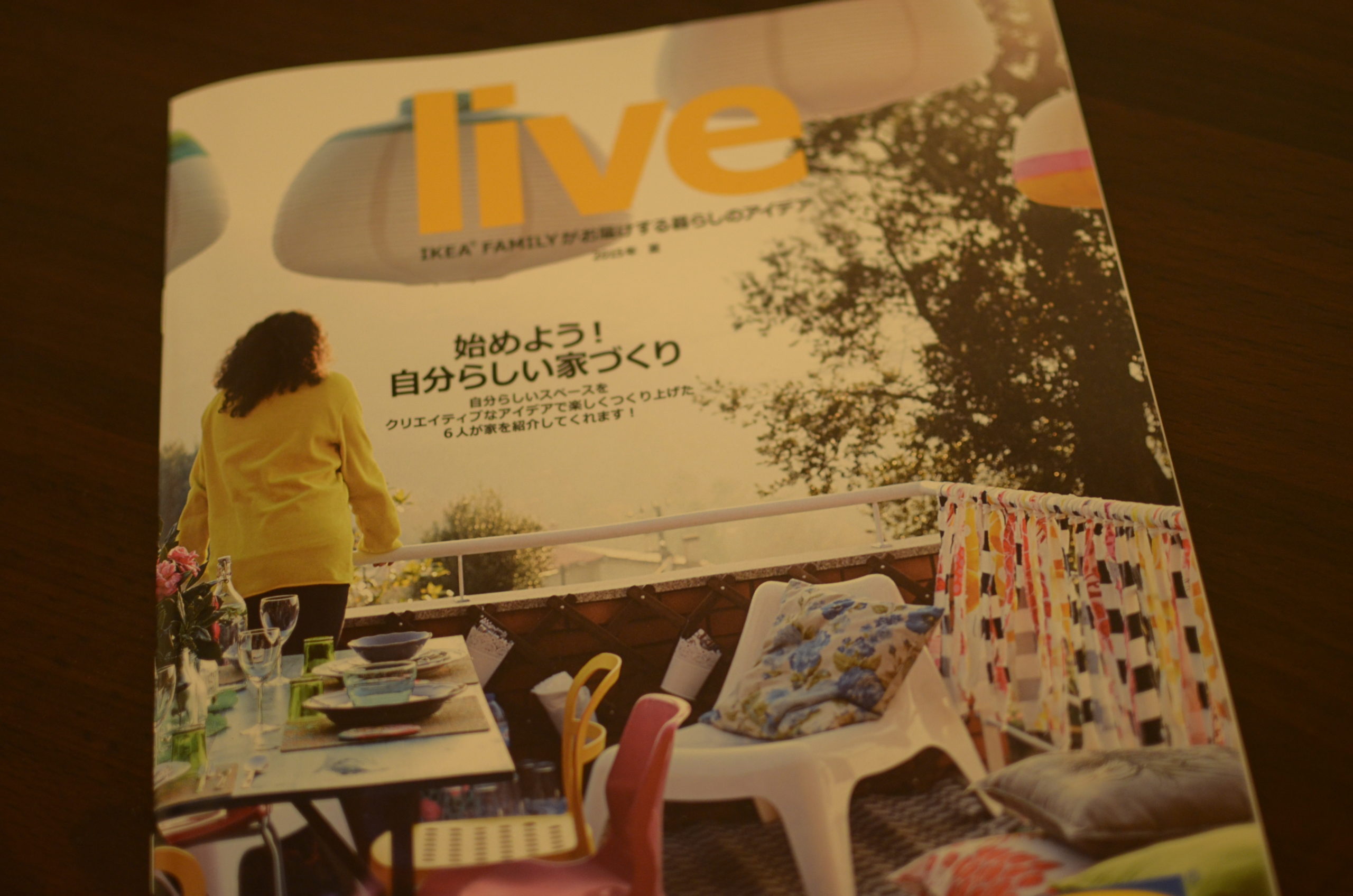いちおう簿記3級まではとったのですが、そこから決算書や会計からは逃げておりました。
ただ、経営者でもあるので、会計というか決算書のひとつもしっかり読めるようになっておこないといけないなぁと常々思っており、折を見ては会計に関する本を読んでいましたが、どれもピンと来ないんです。
それでも懲りずに読んでいたら、いい出会いがありました。
『儲けにつながる「会計の公式」―借金を返すと儲かるのか?』
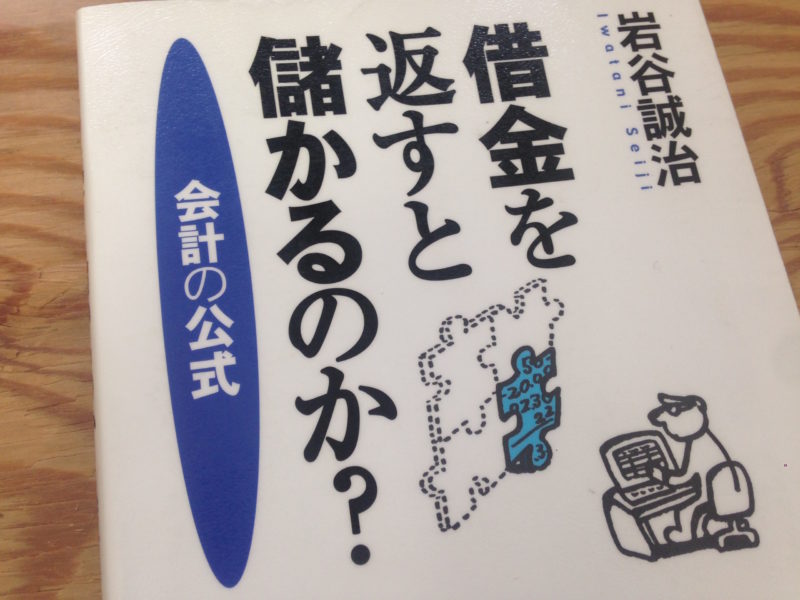
2009年に発売された本ですが、会計の概念をつかむのには相当な良書だと思います。はじめに断っておくと、この本読んでも簿記の試験には通りません。
これは著者も本の中で言っていますが、あくまでも会計の概念をつかむための本です。なので、簿記特有の仕分けの話などはほとんど出てきません。ただ、概念をつかめるので、簿記の勉強を始める前に読んでおくとその後の理解スピードにめちゃくちゃ差が出ると思いますので、事前に読んでおくと良いと思います。
パズルの組み合わせ
会計というとすぐに難しく感じるのは、仕分け用語に惑わされているからと著者は言われており、自分もそのとおりだと思います。
なんかややこしい用語と数字に騙されて、それだけで嫌になっちゃう。営業や経営者にとって、大事なのはそんな細かい用語ではなく、決算書から何が見えるかだと思うのですが、本書はその点に絞って書かれているため理解しやすかったです。
会計に登場する「資産」「負債」「資本」「収益」「費用」の5つのブロックに発生した取引を当てはめていくというだけです。
今までこれをややこしく感じていましたが、ざっくりと分類できるようになります。取引については、左右両方のブロックに取引を振り分ける必要がありますが、その組み合わせについても著者は相当噛み砕いて説明してくれています。
究極は、下記の一文だけ覚えておけば大丈夫としてくれています。
資産が増えて利益が減ることはない
このルールさえ覚えておけば大丈夫というのですから、相当楽です。
ルールはテトリスと一緒
それから反対取引については、著者はテトリスを例に説明されています。テトリスと一緒でブロックを消していく作業と考えると理解しやすいので、例えば、借入金を返済したので、その取引を消すには、反対側に借入金を持って行くとそのブロックは消すことができると考えるとわかりやすいです。
新しい視点で決算書をみることができる
本書を読む際には、決算書が手元にあるとさらに理解しやすいと思います。
決算書は上場会社ならサイトから簡単に見られるので、プリントアウトしておいてから読むと著書がいう決算書の見方がその場で試すことができると思います。
本書を読み終えると、決算書からを見る視点が多元的になっていると思います。企業は利益を残すためにその活動を行っていますが、当然ながら売上をあげるだけでは利益を最大化することはできません。
仕入原価を下げることでも利益を増やすことはできますし、資産の収益性をあげることでも利益を増やすことができます。単純に収益を上げ、費用を抑えるだけの視点から、もっとたくさんの要素で利益が変わってくることを読み取れるようになります。
集中すればすぐに読める本なので、時々読み返しながら決算書からいろいろと読み取れるようになりたいです。まずは自社の決算書でいろいろ思考してみます。