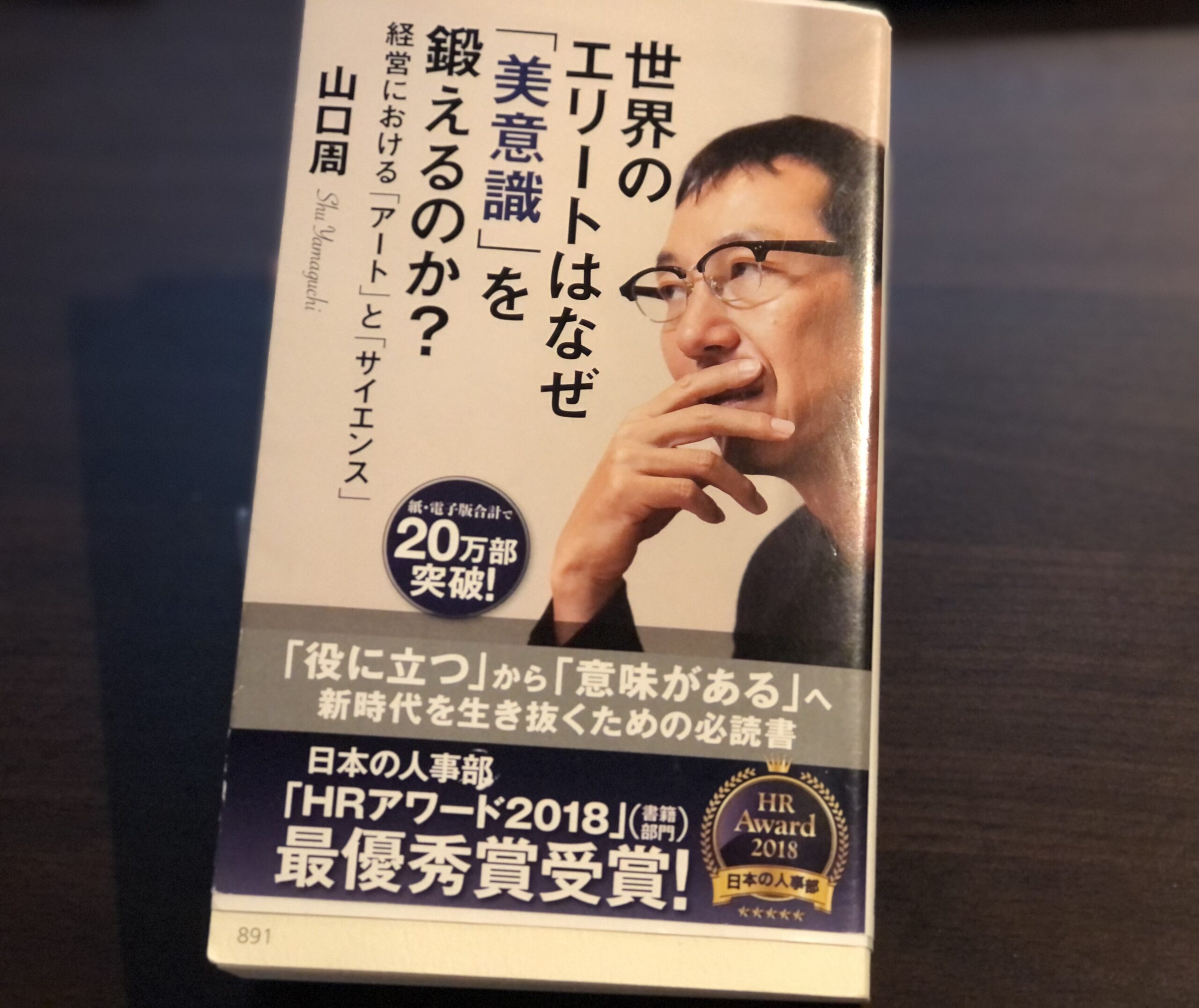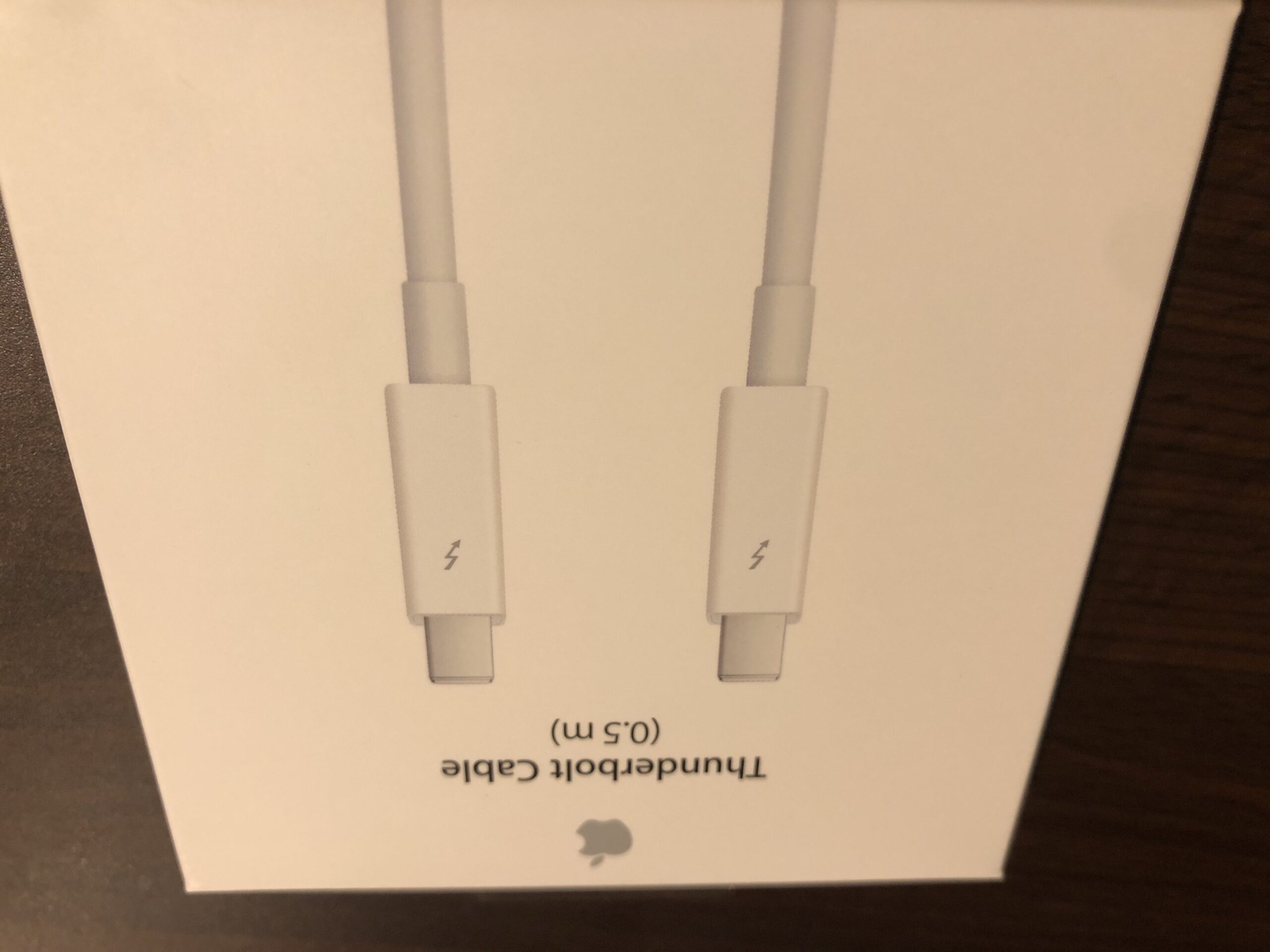最近の決算状況等を見ていると社長の顔が見えている企業が強い気がします。
例えばユニクロの柳井社長、ソフトバンクの孫社長、トヨタの豊田章男社長、世界に目を向けるとテスラのイーロンマスク、アップルのスティーブジョブスなどがいます。
なぜ社長の顔が見えている会社が好調なのか気になって本書「なぜエリートは美意識を鍛えるのか」を読んでみました。
なぜエリートは美意識を鍛えるのか
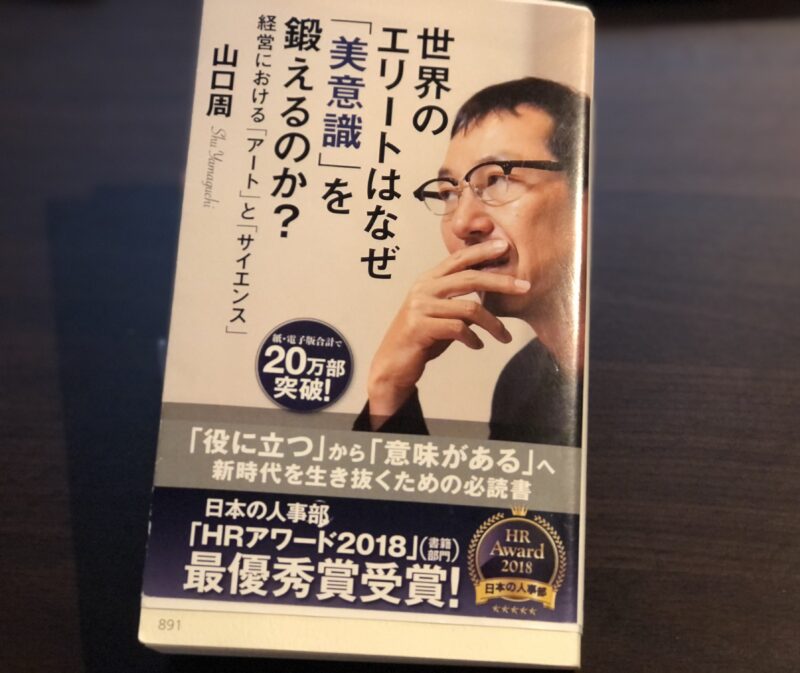
以前は、というか2000年頃までは、論理的であることが礼賛されていました。
戦略コンサルティングファームが興盛だったのもこの頃です。
ただ、論理が幅をきかせすぎると、他の人と同じ答えが出せると言うことでもあります。
他の人も同じよなマーケティングリサーチをおこない、同じような論理に基づいて商品やサービスを作るようになる。
つまりレッドオーシャンでの戦いになります。
そこにアート的思考が入ると、論理的な競争とは無縁のところで戦えます。
でも、アートな意思決定は、論理では説明できません。
なんとなく良いと思って
自分はなんとなくこの商品が良いと思うんだよね。
これで商品開発にGoを出せるのは、創業社長や圧倒的なパワーをもつ社長だけです。
本書では、そういった本「アート」的な考えとの対比で「サイエンス」と「クラフト」という考えも紹介されています。
サイエンスに基づく判断は、情報分析の結果です。つまりは、マーケティング・リサーチやフレームワークですね。
クラフトは過去の経験に基づいた判断ということになります。
「アート」vs「サイエンス」&「クラフト」
「サイエンス」、「クラフト」の主張は論理的に説明できます。ですが、アートの主張は何となく良いと思う、つまり「直感」です。
この2つが戦うとどうなるかは火を見るより明らかです。
日本の大企業で「アート」の主張が通ることはまずないでしょう。
でも、創業社長やちからのある社長であれば「アート」を通すことができます。
ここに、顔の見える社長のいる会社が強い理由があるように思います。
本書でお勧めされているのはトップ(CEO)にアートの担い手をおき、そして脇の陣営にクラフトタイプの人(COO)とサイエンスタイプの人(CFO)で固めるのが良いのではないかと言われています。
もしくは経営トップがアートの担い手に大きな権限委譲をする。
ユニクロはまさにこのタイプで、アートディレクターの佐藤可士和さんが戦略アドバイザーとして柳井さんと2人3脚でグローバル展開を進めています。
こういう時代なので、他と同じことをやっていても先は見えています。
文学を読む
論理的思考に行き詰まったら文学を読むことも推奨されています。
エリートが時として、犯罪を犯す背景に文学に触れていないことにも本書の後半で触れられています。
アートタイプの思考には、絵画にふれることや文学にふれることが必要なのかもしれません。
そう言われてみると、イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグはSF小説を好んで読んでいるという記事を見たことがあります。
元マイクロソフト社長でHONZを主催する成毛氏もSF小説を読むことは事あるごとに勧めていることを思い出しました。
アートディレクターがトップの会社
自分は、近々新しいビジネスで一つ会社を立ち上げようとしていたのですが、本書を読んでアートを担える人を代表にしてみようかと思っています。
自分はどう考えても、サイエンスとクラフトタイプですので。
論理的な思考でしか物事を考えられなくなっている人にぜひ読んでもらいたい一冊です。