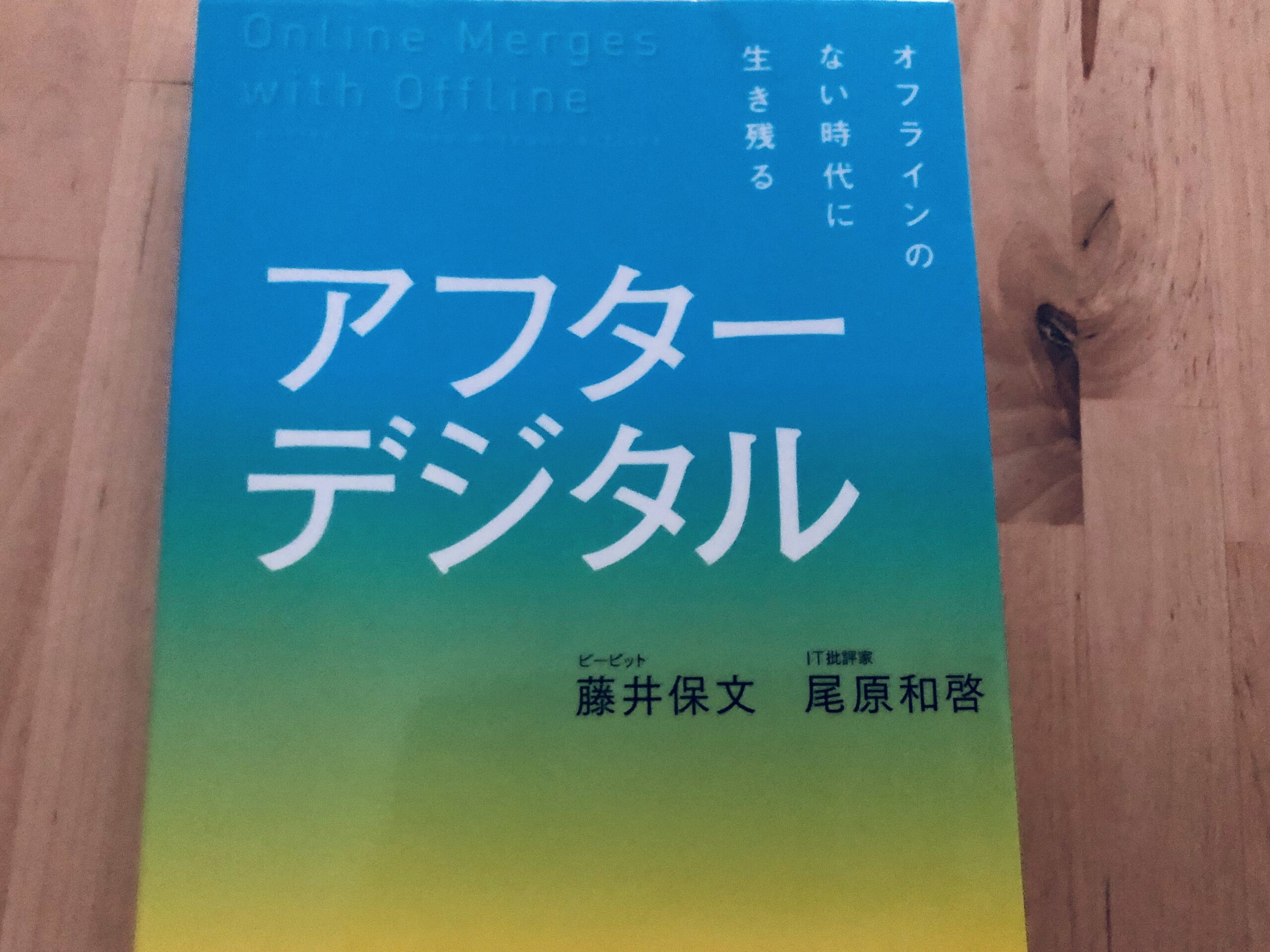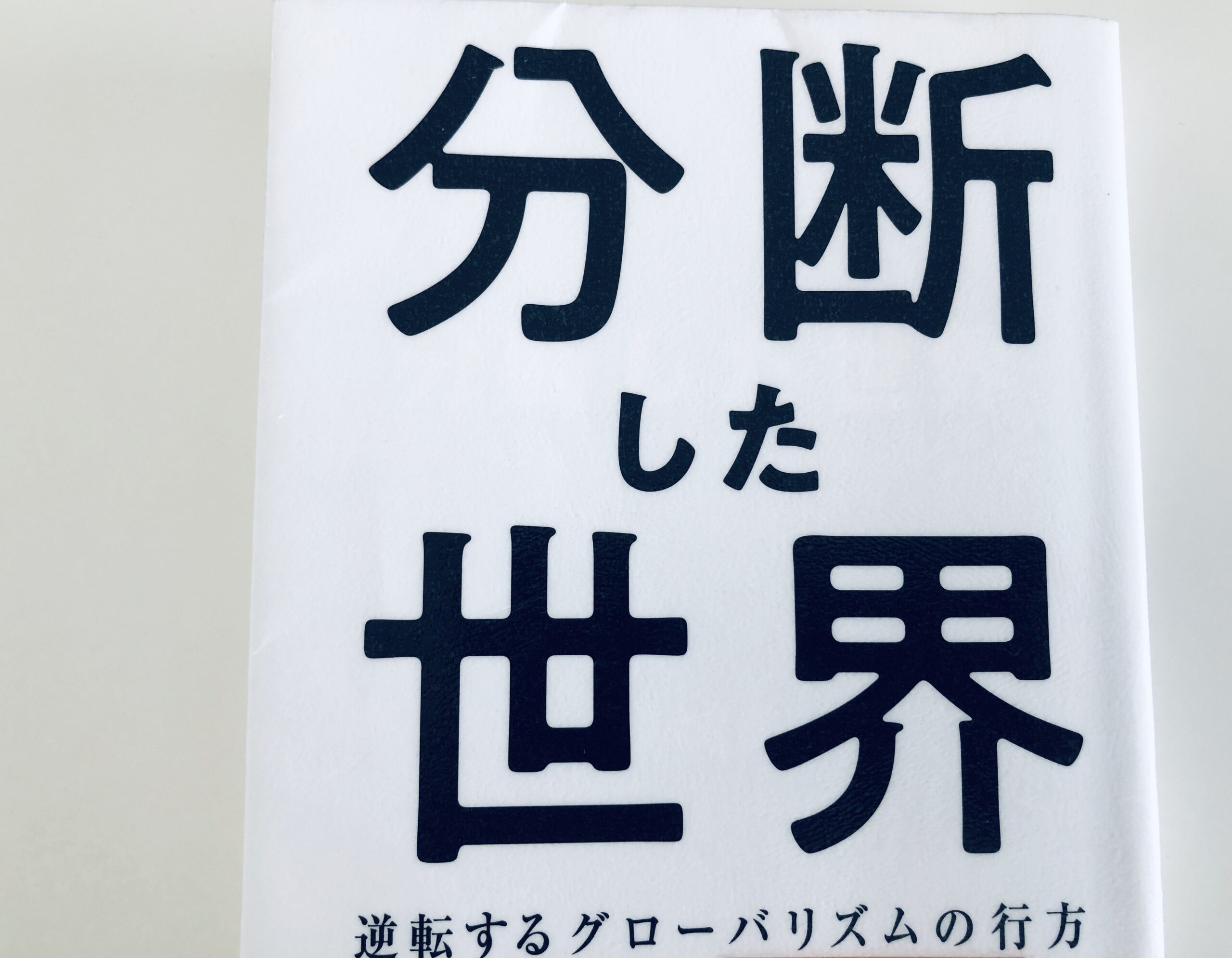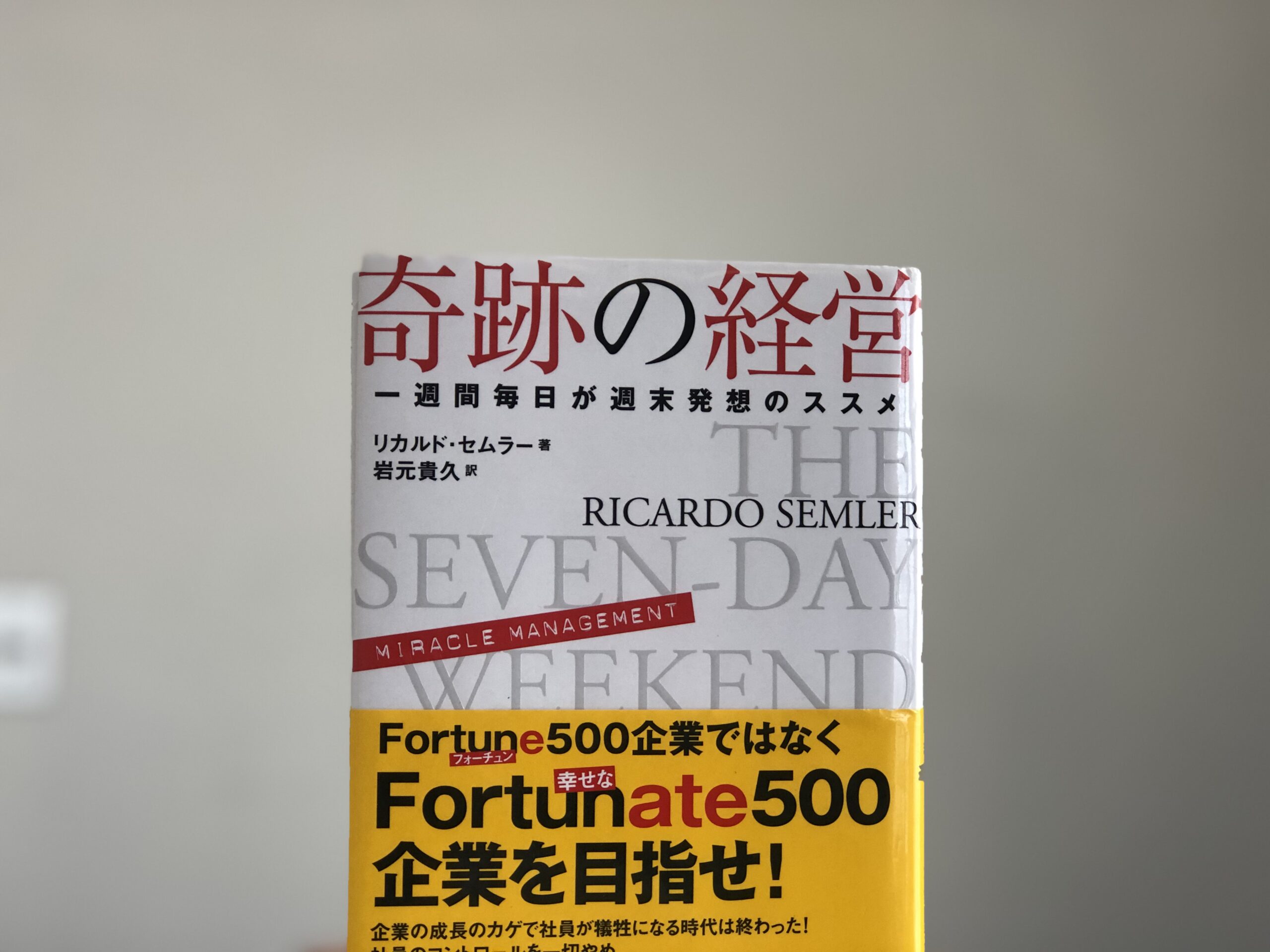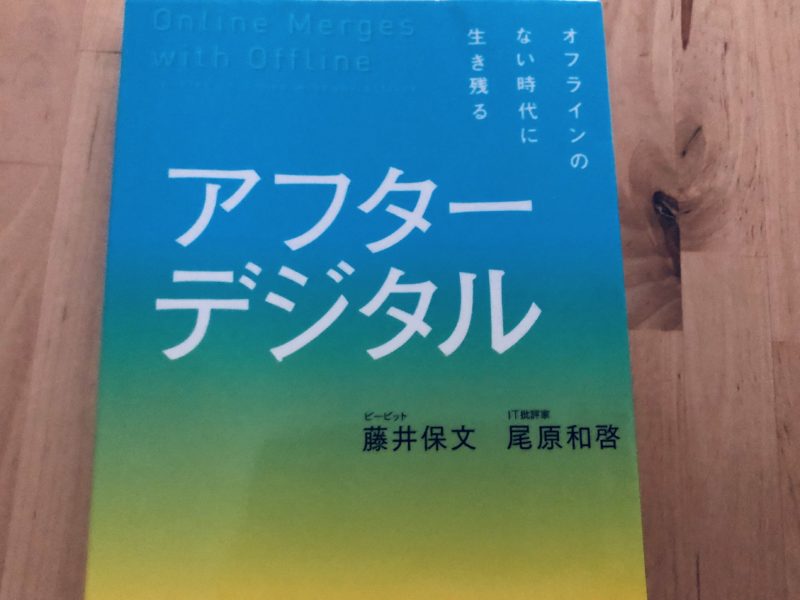
「オフラインのない時代に生き残る」という副題に惹かれ、ビービットの藤井氏、IT批評家の尾原氏による共著「アフターデジタル」を読みました。
本書では、ビフォアデジタルとはリアルで会える人がたまにデジタルに来る世界、それに対して、アフターデジタルはオンラインで絶えず接点があり、たまにデジタルを活用したリアルにも来てくれる世界とオフラインのない世界を表現されています。
アフターデジタルは、ビフォアデジタルの延長線にはないことを示唆しています。
オフラインでの発想をそのままオンラインに持ってくるのではなく、オンラインの発想をオフラインに当てはめるにはどうすればよいのか?という視点でアフターデジタルの世界が描かれています。
オンラインの企業が無人コンビニをつくるのは、いかにオフラインのデータを取得するかの実験のためとジンドンの幹部が言うのも納得です。
そして、モバイルもPCBもコンビニも一つのユーザーインターフェースでしかないと言い切っています。
ユーザーはオンラインか、オフラインかなど意識せずにその時に便利な方法で買うので、その方法を用意する必要があるともいいます。
オンライン店舗も実店舗も、ただのインターフェースと捉え、集めたデータをもとに最適解を導き出していくのが、アフターデジタルと言えそうです。
その点、日本の企業はいかに今やってるビジネスをオフラインで展開するかしか考えていないので、その差は歴然です。
本書でも触れられているのですが、ビジネスを1から作り直すくらいでないとアフターデジタルには対応できない。
そう考えると、人件費の安い中国でなぜ無人店舗が多く出てきているのか納得できます。
彼らは、オンラインとオフラインの垣根のない顧客データを集めて、その顧客1人1人に合わせたサービスを展開しようとしています。
ようやくキャッシュレス決済企業が狙っているのはまさにこのオフラインの消費データです。このデータとオンライン上でのデータを合わせることで、顧客1人1人の行動がすべて可視化できます。
ここを見ている企業「Paypay」などは、決済手数料なんて小銭を気にせず、躍起になってシェアを取りに行きますね。
アフターデジタルは、こちらが抗ってもその波はどんどん押し寄せてくるので、もう避けることはできないです。
であれば、しっかりその波に乗れるように今から動き出すべきです。
本書は、アフターデジタルの思想というか、根本の考え方が豊富な事例と共に丁寧に書かれています。
ビジネスに係る全ての人に読んでほしい一冊と言えます。