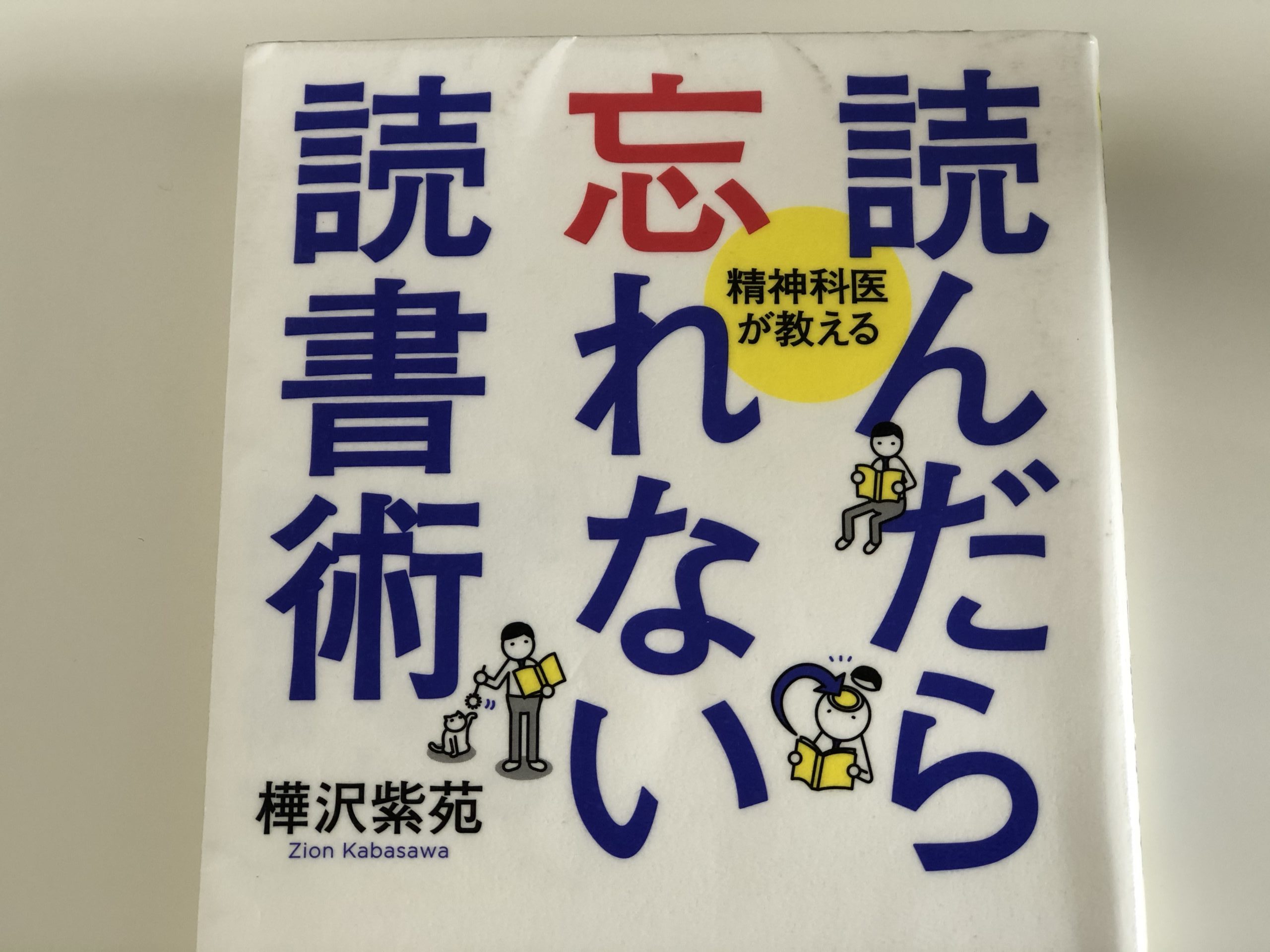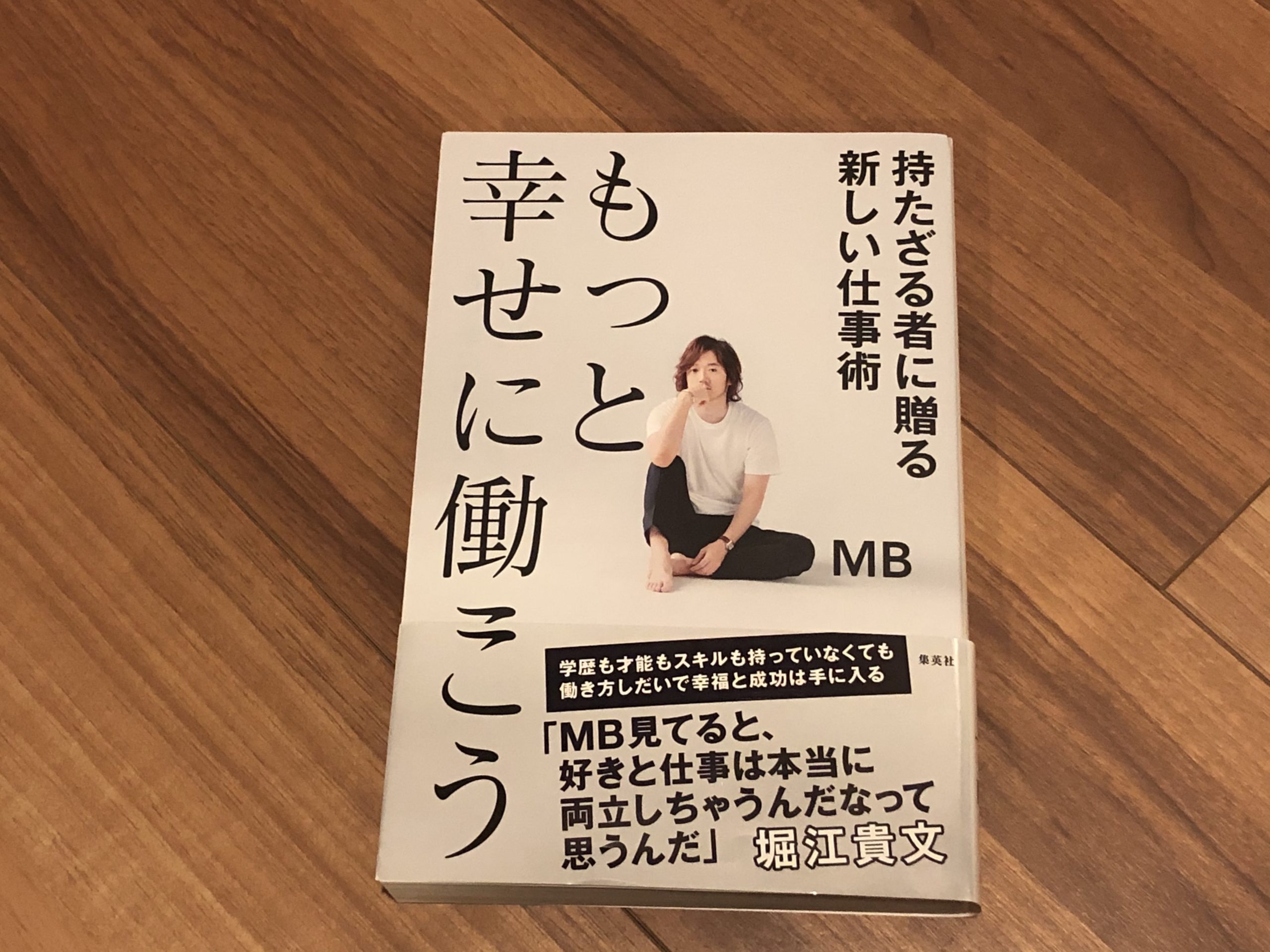新型コロナの影響で家で過ごす時間がめちゃくちゃ長くなりました。
お客さんとの打ち合わせもビデオ会議ですむので、行き帰りの時間とかが短縮できてめちゃくちゃ効率的です。
せっかく時間ができたので、かなりよい調子で本を読めています。
せっかく読んだ本をしっかり自分の知識として活かせるようにしたいと思い、「読んだら忘れない読書術」という本を読んでみました。
読んだら忘れない読書術
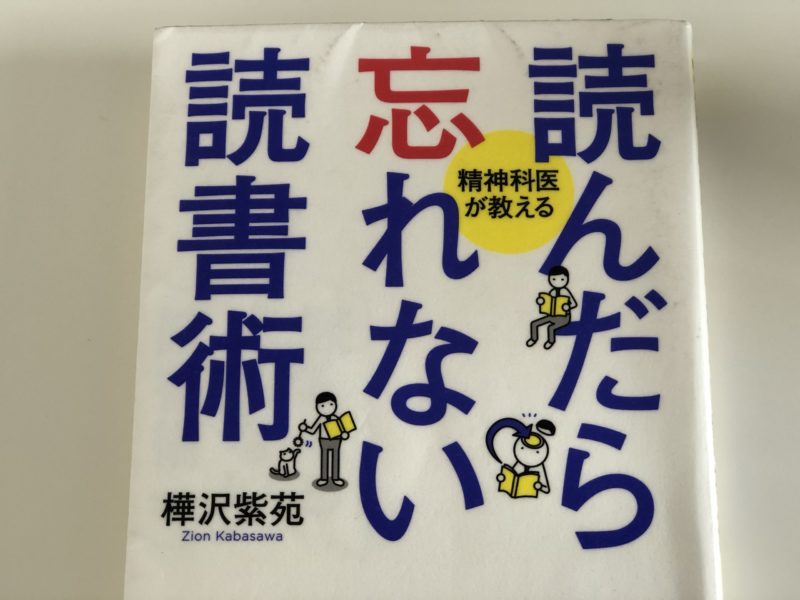
読書を自分の知識とするために、1週間に3回アウトプットをすることがで推奨されています。
- 本の内容を話す
- 本の感想や気づき、名言をFB、Twitterでシェアする
- ブログやメルマガに書評・レビューを書く
自分はついつい読むことが目的になってしまうことがあるので、本を読んだら3回のアウトプットを忘れずに実行したいと思います。
本を読む際は、まずはパラパラとめくってゴールを決める。
この本を読む目的を最初に決めておくことが大事です。
本を読むことは手段なので、本を読んでどうしたいのか予め決めておくことで、得られる知識は全然変わってきます。
スキマ時間読書術
読書術は時間術ともいわれるように、本を読む時間を確保するのが問題だったりします。
自分も時間ができたら読もうと思って、積ん読になっている本が結構あります。
そうやって思ってるうちは、いつまでも経っても読めないですね。
ちょっとしたスキマ時間があると本を読むようにする。
スマホではなく、本を開く、その癖をつけないといつまでたっても本を読むことができないと著者は言います。
人間は集中して読むことのできる時間は15分くらいなようなので、スケジュールに15分の読書時間を差し込んで行こうと思います。
1冊の本の元を取ろうとしてはいけない
本を読みだすとついつい本の値段分くらいは何か得てやろうと思ってしまいます。
ただ、1冊の本で元をとうろとしてはいけないと著者は言います。
例えば、月に1万円を読書予算にとすると、だいたい6,7冊の本が読めます。
その中で1冊でもいいものがあればいいくらいの気持ちで読む。
本を読む目的に合わないのであれば、読むことをやめることも選択肢のひとつ。
ホームラン級の本に出会えたら何度もその本のエッセンスを自分に憑依させるくらい読み込んでも良いと思います。
外出自粛の今だからこそ、本をしっかり読んで自分をアップデートしたいですね。