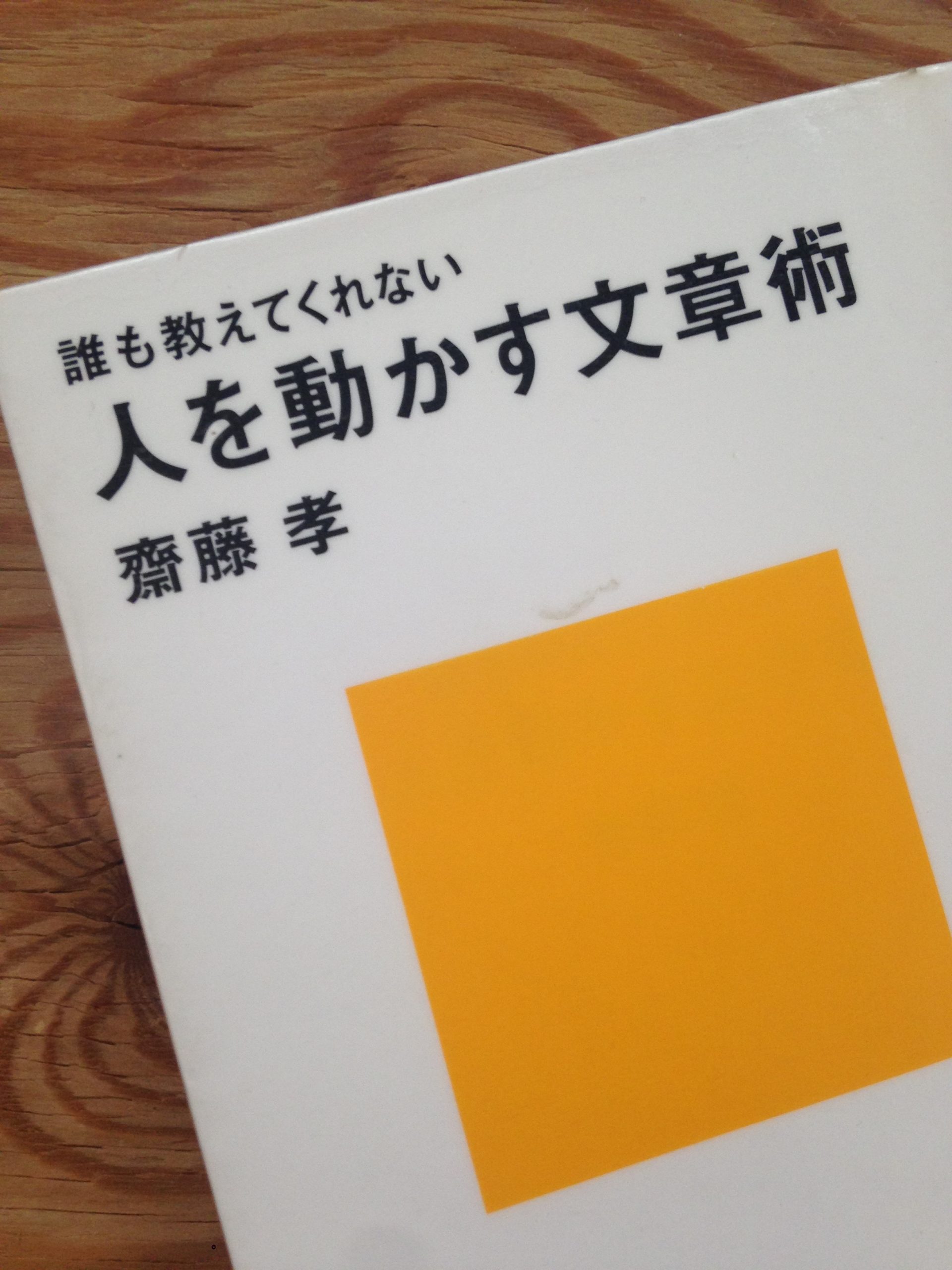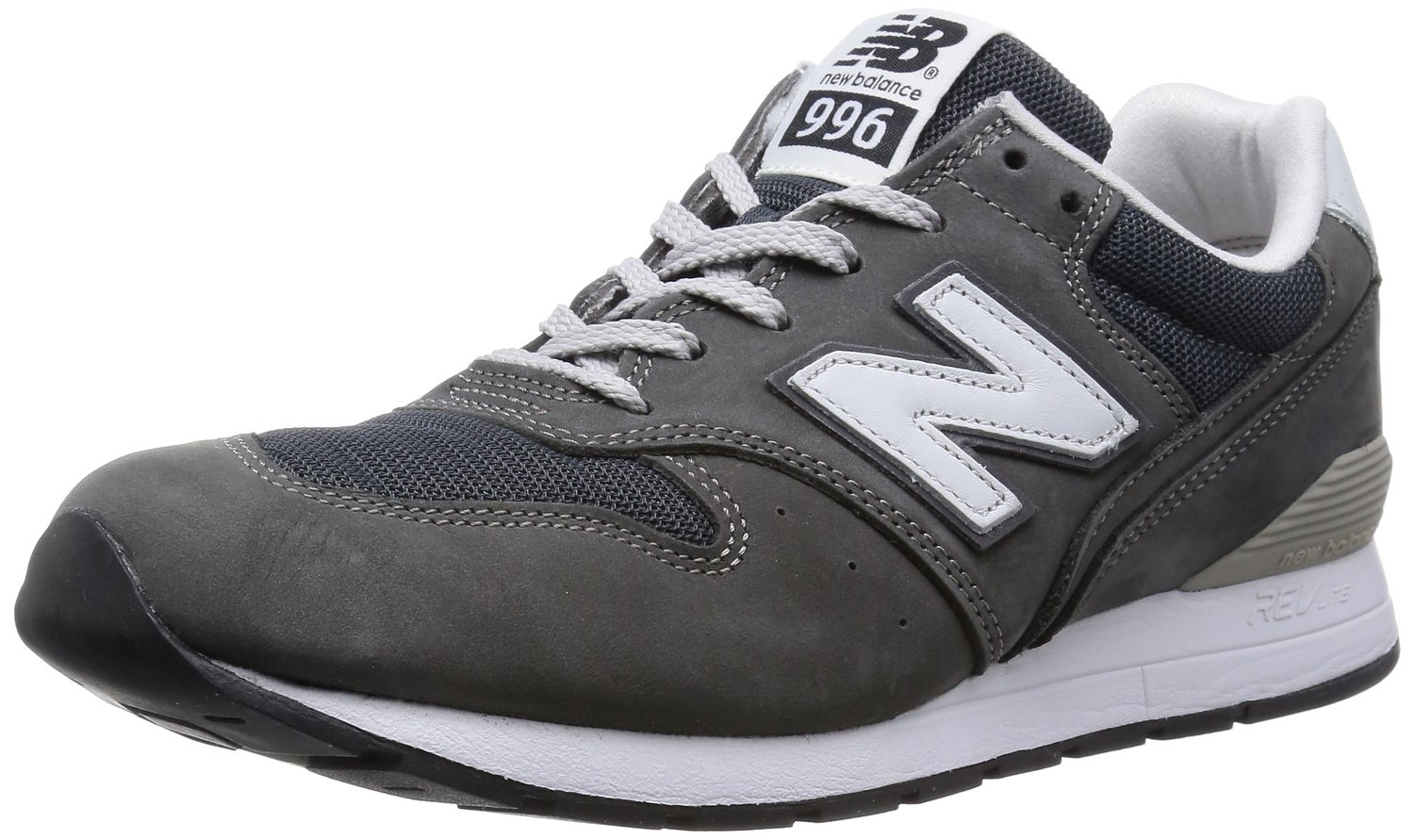社会にでると色々な文章を書く必要があります。報告書、稟議書や提案書など、ほんとに何々書をよく書かされます。
しかしながら、これだけ文章を書くニーズがある割には、実は文章の書き方って学生時代に習った記憶がほとんどありません。
なのに、会社入った途端いきなり色々な文章を書くことが求められます。メールにしてもそうですよね。でも、社会人になっても誰も文章の書き方は教えてくれないです。
人を動かす文章術
斉藤孝氏の『人を動かす文章術』では、そんな誰も教えてくれなかった文章術を丁寧に教えてくれています。
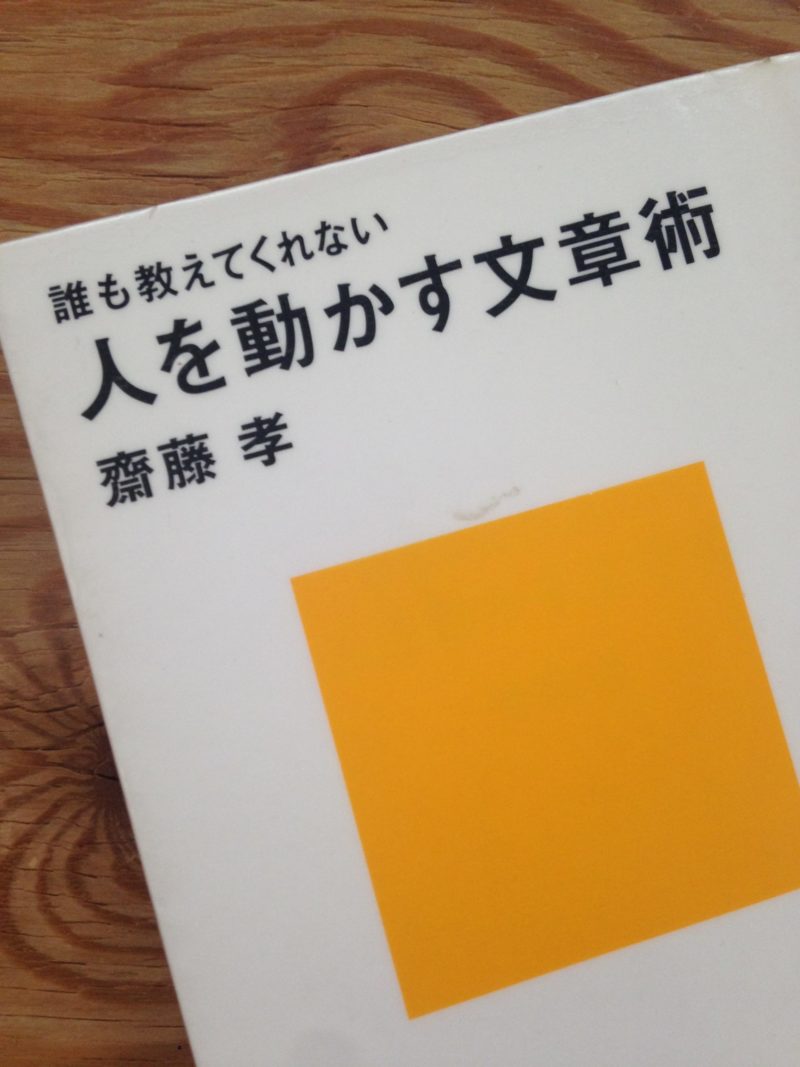
まずはゴールに集中する
日本人が文章を書くと言う時に、まず思いつく「起承転結」という文章スタイル。
この方法は元は中国の詩のかたちから来ているスタイルですが、物語などでストーリー変化として起承転結スタイルは有効だとしながらも、実用的な文章では、そんなふうに恰好をつける必要はなとバッサリです。
提案書にもやたらと起承転結にこだわる上司がいたけど、確かにあの人アウトプットは遅かったもんなぁ。まずはゴール、ゴールに一直線で辿り着く文章を創る。そのために、ゴールから設定する。
つまりは、結論となる一文です。
認識の面白さ
結論となる一文では凡庸なものは絶対避けるべきだと著者は言っています。
凡庸は恥とまで言い切っているので、ぜったい「思いやりは大切だと思った」とか書いちゃいけない。自分にしかできない認識をこの一文に込めるくらいでないと、人に伝わる文章というのは書くことはできない。
それこそ、全身全霊魂を込めて取り組むのがこの一文です。その際、普通つながらないであろうものがつながっているのが面白い文章。
同質であると思われているところから異質を見つける能力と言うべきのものがその人の持つ認識の面白さだと言い、それを最後の一文に持ってくる。
結局、個性ってある種無理やゆがみであって、それはないわって思わせながらも、さもあるように思わせれたらその文章は勝ちです。
タイトルはゴールへの疑問文
ゴールが決まるとタイトルを決めます。
文章のスタートとなるタイトルで大事なのは、読者の心を一気につかめるもことです。そのためには、タイトルをゴールに対する疑問文の形にすることを著者はおすすめしています。
タイトルでしっかり読者を掴んで、ゴールではその疑問が解決している状態です。そこまで決まったら、あとは、三段構えでゴールまで読書を一気に連れいてきます。
三段構えくらいでそのゴールまで多少強引でもいいので持って行くと、文章としては筋が通ります。目標地点が決まっている時は勢いで早く文章が書けるようになるはずと言っています。
起承転結呪縛からの開放
まずゴールとなる結論の一文を決めて、それからスタートとなるタイトルを疑問文の形で示す。
その上で、通過駅というべきポイントを三点ぐらいならべるのが読んでもらえる文章。起承転結の起の時も出てきません。文章というとすぐに起承転結に縛られて地蔵になっていたことを思うと本書にはほんとに救われました。
本書では、他にもシーン別に文章の書き方が紹介されているので、その文章を書く際には是非目を通すといいと思います。
特に履歴書の書き方は非常に参考になるので、就活生はまず読んでおいて損は無いです。現代人にとって、必須のスキルである文章術は身につけておいて、プラスはあってもマイナスは全くないものです。
それをこの1冊で身につけられると思うとほんとに本の費用対効果は計り知れないです。
だから読書はやめられないです。